大学受験で特になってくるのは「出願戦略」だ。
今の時期に生徒/保護者様が頭を抱えているのは、志望校選びだと思う。
毎年のように、大学受験を甘く見て
「安全校を受けない」「挑戦ばかり」「実力相応校が抜けている」——そんな受験生を見てきた。
結果、合格のチャンスを逃す生徒が少なくない。
忘れてはいけないのは、大学受験は想像以上に厳しい戦いだということ。
ほとんどの大学の倍率は2倍を超える。つまり、受ける人の半分以上は落ちるという現実。
① 挑戦校・実力相応校・安全校の定義
志望校は「三角」ではなく「菱形」で考える。
どれかに偏るのではなく、バランスを取って配置することが大切。
- 挑戦校(当日ベストパフォーマンスが出せれば合格できる大学)
合格可能性は20〜30%。届くかどうかギリギリのライン。
ただし、受験勉強の方向性を決める大切な指標になる。 - 実力相応校(実力がそのまま出せれば合格できる大学)
合格可能性は60〜70%。最も中心となる大学群。
ここで合格を掴めるかどうかが、受験の成否を分ける。 - 安全校(確実に合格を取る大学)
合格可能性は80〜90%。いわば“保険”ではなく“安心材料”。
合格通知が手元にある状態で挑戦校を受ける方が、精神的にも強い。
② 「菱形」で受けるという考え方
理想の受験校リストはこうだ。
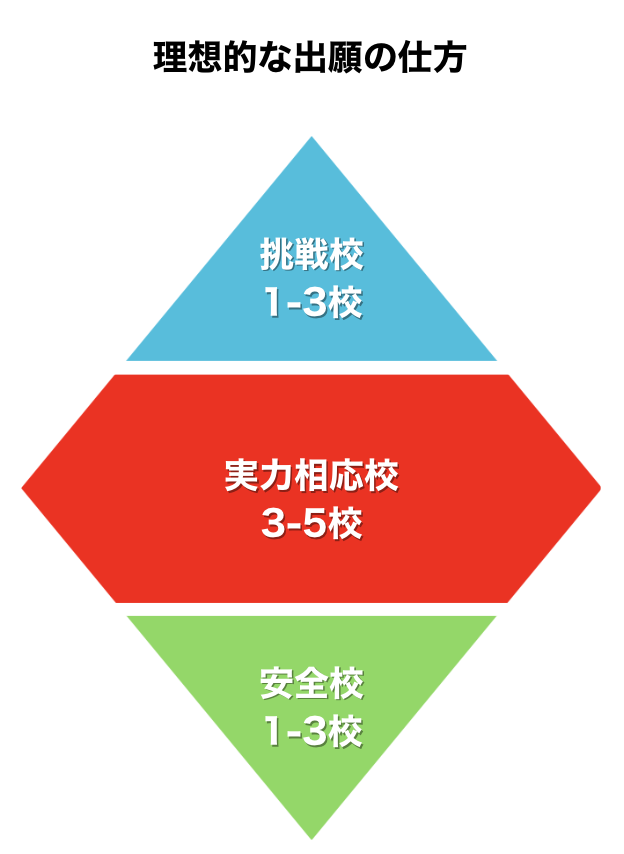
この形を意識して受験校を選ぶ。
挑戦と現実の両方を見据えた“菱形受験”が、最も安定して合格をつかめる。
③ 現実的な条件も大事にする
志望校は偏差値だけで選ぶものではない。
たとえば、通学時間。
電車に乗っている時間が1時間以内というのが理想。
よっぽど行きたい大学があるという場合を除いて、通学に往復3時間かかるような環境では、大学生活そのものが苦しくなる。
また、「大学の雰囲気」「学部の内容」「将来の進路とのつながり」も重要。
パンフレットだけでなく、実際に足を運んでみること。
五感で感じた印象は、案外正確。
④ 志望校レベルの設定方法(12月1日時点の目安)
志望校レベルを決めるうえで大切なのは、
模試の偏差値だけでなく「正答率」と「時間内処理力」で判断すること。
EIMEIでは、12月1日時点で以下の基準を目安としている。
| 分類 | 正答率の目安 | 時間感覚 | 到達イメージ |
|---|---|---|---|
| 挑戦校 | 60%前後 | 時間オーバー5〜10分はOK | まだ余裕はないが、解法や思考の筋道は見えてきている段階 |
| 実力相応校 | 約75% | 時間内に収まる | 実力がそのまま結果に反映される安定ゾーン |
| 安全校 | 約80%以上 | 5分程度余る | 精度・スピードともに余裕がある状態。確実に合格を取れる |
つまり、「正答率×時間」=実力の現実値。
どちらか一方だけでは正確な判断ができない。
例えば、
- 正答率80%でも10分オーバーなら、まだ安全校レベルとは言えない。
- 正答率60%でも時間をかけすぎず取れているなら、挑戦校として十分戦える。
受験までの残り期間で、
- 「挑戦校」で60%→70%へ精度を上げる
- 「実力相応校」で安定的に合格ラインを維持する
- 「安全校」で確実に取り切る
この3層のバランスを意識して勉強を進めることが、12月以降の最短ルートになる。
⑤ まとめ 〜勝つ受験生の志望校設計〜
志望校選びは「今の自分」と「なりたい自分」をつなぐ架け橋。
挑戦は必要だ。だが、戦略のない挑戦はただの無謀。
偏差値と正答率、時間感覚、通学条件まで含めて冷静に判断すること。
そして、挑戦と現実の両方を叶える「菱形受験」で臨もう。
