〜共通テスト模試(英語)と“受験勉強の序盤”が噛み合わない理由〜
三者面談の中で、保護者の方からよくこんな声を耳にします。
「最近は勉強してるんですけど、共通テスト模試の点数が全然伸びなくて…」
お気持ち、よくわかります。
「頑張っているのに点数に表れない」と、保護者様としては不安になりますよね。
生徒も同様に「なんでこんなに勉強しているのに期待しているほど点数が上がってないんだ」
と落ち込む人もいると思います。
もちろん、まずは自分の勉強時間・量を見直すべきです。
でもそれだけでなく、ここに一つ知っておいていただきたい「ズレ」があります。
共通テスト英語で問われているのは、“知識”ではなく“読解力”
共通テストの英語は、かつてのセンター試験や私立大学の入試問題とは違い、
文法や単語といった「知識問題」はほとんど出ません。
代わりに出るのは、
実生活をベースにした長文(メール・掲示板・プレゼン資料など)や小説文、評論文を読んで、情報を素早く正確に読み取る問題。
つまり、「知ってる」よりも「読める」ことが大切なのです。
受験勉強の序盤は、“知識インプット期”
一方で、受験勉強の序盤は、
単語・文法・構文・基本英文解釈…といった基礎の積み上げが中心になります。
これは当然のこと。
読めるようになるには、語彙力や文構造の理解が必要です。
でもこの時期、その努力がまだ“長文読解の得点”には結びつきづらいのです。
だからこそ、
「勉強してるのに、模試の点が伸びない…!」
というモヤモヤが生まれます。
英語以外の科目は??
他の科目でも同様に、公式を覚えたらすぐに模試で点数が上がるわけではありません。
勉強はスポーツのようなものだと生徒に伝えることがあります。
①まずは知識(コツ)を先生やコーチから教わる→インプット
②練習で意識してやってみる(最初は失敗することのほうが多い)→アウトプット
③本番で無意識レベルで練習の成果を安定して出せるようになる→成長(模試での点数や過去問の点数アップ)
例えば、サッカー初心者にいきなりオーバーヘッドキック(英語で言うと発展レベルの長文問題)を教える指導者はいません。
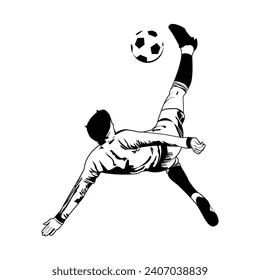
まずは何よりも基礎の反復が大切になります。
このように模試の点数に反映されるためには踏まなければならないステップがあり、根気強くそれらを継続する必要があります。
共通テスト対策、いつ・どこまでやるべき?
ここでよく聞かれるのが、
「じゃあ、共通テストのための勉強って、いつからすればいいの?」
という質問。
答えはシンプルで、
一般入試がメインの人は、基本的には秋以降で十分です。
もちろん、志望校によって共テ利用の比重は異なります。
共通テストが合否に関わる場合(国立受験者など)は、夏以降(8月ごろ)に長文読解演習に入り「共テの読み方」に慣れていけばOK。
序盤の今は、焦らず“読める力”の土台をつくることに集中すべきです。
じゃあ、「順調にいってる」ってどう判断すればいいの?
模試の点数に一喜一憂するのではなく、
大学の過去問を軸に判断するのがおすすめです。
たとえば、
- ●●大学の英語では「7.5割」が合格ライン
- そのために、9月末までにこの参考書を終わらせたい
- 今の進捗なら、8月までに基礎が固まりそう
——こんなふうに、ゴールから逆算して今の勉強を評価することがとても大事です。
今やっていることは、必ず“伸びる”ための準備
受験は、長期戦です。
種を蒔いて、根を張って、芽が出るまでに時間がかかります。
特に英語は、
「読めるようになるまでの時間差」がある教科。
焦らず、でも確実に、力をつけていくこと。
それがこの夏、そして秋以降の“爆伸び”につながります。
「今は伸びない時期」と知っているだけで、
目の前の努力が報われる日を信じて進めるはずです。
